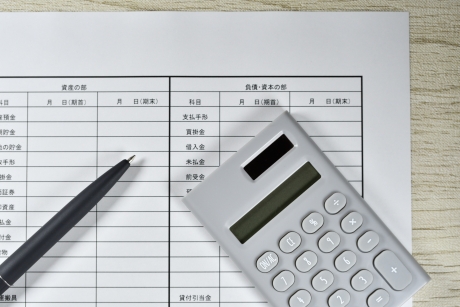投稿日:2025.08.01 最終更新日:2025.08.01
事業承継時に「税理士」を見直す理由は?会社の未来を決める“攻めの経営”を徹底解説!

事業承継は、多くの後継者にとって、まさに「第二の創業」ともいえる大きな決断のときです。先代が築き上げた大切な会社を、自分の手でさらに発展させていきたい。
その大きな志とは裏腹に、「先代からの付き合いで、今の税理士には本音が言えない……」 「今の先生は、税金の計算はしてくれるけど、会社の未来についての相談はどこか他人行儀だ……」
そんな、誰にも言えない葛藤を抱えてはいませんか?
実は、事業承継というタイミングは、会社の未来を共に創るパートナーとして、税理士という存在を根本から見直す、またとない機会なのです。
とはいえ、いざ変更するとなると、「どんな基準で選べばいいのか」「今の税理士との関係はどうなるのか」と、新たな不安が生まれるのも当然でしょう。
この記事では、事業承継を機に税理士の変更を真剣に考える後継者の方へ、なぜ「今」がベストタイミングなのか、そして会社の未来を本当に託せるパートナーをどう見極めるべきか、その本質的な判断基準を、専門家の視点から詳しく解説していきます!
- 事業承継を成功させるために、後継者がまずやるべきこと
- 事業承継のタイミングで税理士を見直すべき本当の理由
- 今の税理士への不満につながる根本的な原因
- 会社の成長を加速させる「未来志向の税理士」の見分け方
- 税理士変更の具体的な手続きと、失敗しないための注意点
南 彰悟
1986年3月6日生まれ。大分県出身。早稲田大学を卒業後、25歳で公認会計士試験に合格。大手監査法人に8年程勤める。2020年税理士登録。イデア総研税理士法人の副代表として活動する。
大前提:事業承継で後継者がやるべきこととは?

税理士の変更を考える前に、まず、事業承継という大きなプロジェクトの全体像を把握しておくことが大切です。後継者として取り組むべき課題は、決して数個ではありません。
経営のバトンタッチ:6つの重要タスク
後継者が主体的に進めるべき経営面のタスクは、大きく6つに整理されます。
- 会社の健康診断(経営状況の把握): 財務状況はもちろん、事業の強みや弱みを正確に診断します。
- 未来への航海図(事業承継計画の策定): いつ、誰に、どのように事業を引き継ぐのか、具体的な計画を描きます。
- 会社の魅力アップ(企業価値の向上): 事業の強みをさらに伸ばし、弱点を克服して、会社の魅力を高めます。
- 経営者としての器(後継者のスキルアップ): 経営者に必要な知識やリーダーシップを磨きます。
- 信頼のネットワークづくり(社内外の人間関係構築): 従業員、取引先、金融機関との新しい信頼関係を築きます。
- お金の計画(納税・運転資金の準備): 相続・贈与税の納税資金や、事業を継続していくための運転資金を計画的に準備します。
これらは互いに複雑に絡み合っており、どれか一つでも欠けると、承継後の経営はうまくいきません。
人や組織の引き継ぎで、見落とされがちなポイント
事業の引き継ぎでは、「人」と「組織」の問題も避けては通れません。
- 法的な手続き: 役員変更や株式譲渡など、法律に定められた手続きを漏れなく進める必要があります。
- 新しいルールづくり: 新しい経営方針に合わせて、就業規則や評価制度を見直すことも重要です。
- 隠れたリスクの洗い出し: 未払い残業代や労務トラブルなど、目に見えないリスクがないか、事前にしっかりチェックしておく必要があります。
- 古参社員との軋轢: 経営方針の変更に対する反発など、新旧の価値観の違いから生まれる摩擦も想定しておくべきです。
これらの課題に丁寧に対処していくことこそが、スムーズな事業承継の土台となるのです。経営、人事、資金計画など…事業承継時はやること・決めることが非常に多くあります。
【その上で】なぜ税理士を変えるべき?

事業承継で浮上する様々な課題。その中心には、常に「お金」の問題があります。そして、そのお金、つまり「資金管理」に対する不満こそが、多くの後継者が税理士の変更を意識する、もっとも大きなきっかけになっています。
「過去の計算」だけが税理士の仕事ではない
従来の税理士の仕事といえば、「記帳代行」や「税務申告」といった、いわば「過去の数字」を正確に処理することが中心でした。
しかし、会社を未来へ向かって成長させていくためには、過去を計算するだけでは明らかに力不足です。
- 未来のための資金調達: 新規事業や設備投資に必要なお金を、どうやって銀行から借りるか。
- 会社の成長戦略: 未来のビジョンを、具体的な数字の目標に落とし込む手伝い。
- 賢い節税対策: 会社の状況に合わせて、法律の範囲内で最も有利な節税を提案してくれるか。
- もらえるお金の活用: 国や自治体が出している補助金や助成金の最新情報を教えてくれ、申請を手伝ってくれるか。
これらはすべて、会社の未来を創るための「攻めの資金管理」です。
もし、今の税理士がこうした未来志向の相談に乗ってくれないのだとしたら、それは会社の成長の芽を摘んでしまっていることと同じなのかもしれません。
なぜ事業承継は、税理士変更のベストタイミングなのか?
事業承継は、会社にとって大きな変革期です。守りから攻めへ。会社の舵を大きく切り直すこのタイミングは、税理士を変更する上で、主に以下の3つの大きなメリットがあります。
- 「会社の未来像」をゼロから共有できる
- 「過去のしがらみ」をリセットできる
- 新しい「経営の武器」を手に入れられる
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
1. 「会社の未来像」をゼロから共有できる
後継者であるあなたには、先代とは違う新しい会社の未来像があるはずです。しかし、長年付き合いのある税理士は、良くも悪くも「これまでのやり方」に慣れきっています。新しい挑戦に、どこか懐疑的かもしれません。
新しい税理士となら、あなたのビジョンを先入観なくゼロから共有し、同じゴールを目指す本当のパートナーになれる可能性があります。固定観念のない、まっさらな視点で、未来の事業計画や資金計画を一緒に描き上げることができるタイミングなのです。
2. 「過去のしがらみ」をリセットできる
「先代がずっとお世話になったから…」この「しがらみ」は、後継者にとって想像以上に重い足かせとなります。不満があっても言えない。疑問があっても聞けない。そんな関係は、会社の未来にとって決してプラスにはなりません。
事業承継という「会社の代替わり」は、この人間関係のしがらみをリセットする、またとない口実になります。過去の慣習に縛られず、新しいパートナーと対等な関係を築く絶好の機会ともいえます。
3. 新しい「経営の武器」を手に入れられる
税理士業界も日進月歩。クラウド会計の導入による効率化、最新の補助金情報を活用した資金調達、DX化の推進支援など、税理士が提供できる価値は、もはや税務申告だけではありません。新しい税理士を迎えることは、これまで自社にはなかった新しい経営の視点やノウハウという「武器」を手に入れることに他なりません。会社の経営を、根本からアップデートするチャンスなのです。
後悔しないために|税理士変更をスムーズに進める重要ポイント

税理士の変更を決断したら、次はその手続きをいかに円滑に進めるかが重要です。トラブルを避け、スムーズなバトンタッチを実現するために、押さえておくべきポイントを解説します!
手続きの進め方:契約解除と新規契約
まずは、現在の税理士との顧問契約書を確認し、「契約期間」や「解約の申し出時期」をチェックしましょう。一般的には、解約の1〜3ヶ月前には申し入れるのが通例です。
解約の意思は、電話で伝えるだけでなく、書面でも残しておくのが「言った・言わない」のトラブルを防ぐコツです。
その際、これまでの感謝をきちんと伝えた上で、「事業承継による経営方針の変更」を理由に挙げるなど、相手の感情にも配慮した伝え方を心がけることが、円満な関係終了の秘訣です。
最重要ミッション:「暗黙知」の引き継ぎ
税理士の引き継ぎで最も注意すべきなのが、決算書や申告書といった資料には決して残らない情報、いわゆる「暗黙知」の存在です。
- 過去の税務調査で、税務署からどんな指摘を受けたか、どんなやり取りがあったか。
- 会社独自の、特殊な勘定科目の処理ルール。
- 会社の事業内容や、業界特有の慣行に対する深い理解。
これらの情報は、書類だけでは100%伝わりません。
可能であれば、新旧の税理士が直接顔を合わせるミーティングの場を設けるのが理想です。それが難しい場合でも、後任の税理士から前任の税理士へ、電話やメールで直接質問ができるような体制を整えてもらうよう、お願いしてみましょう。
未来を託せる税理士選び、5つの着眼点
では、具体的にどのような基準で新しい税理士を選べばよいのでしょうか。会社の未来を託せる、本物のパートナーを見極めるために、以下の5つの着眼点をご紹介します。
- 「事業承継」の実績と専門知識
- あなたの「業界」への理解度
- 「資金調達」を任せられる支援力
- 「守り」だけでなく「攻め」の経営相談ができるか
- 人としての「相性」
1. 「事業承継」の実績と専門知識
事業承継には、相続税や贈与税の知識はもちろん、株価の評価や組織再編など、複雑な専門知識が不可欠です。
- 事業承継の支援実績は、具体的に何件くらいあるか?
- 相続や贈与に関する専門知識は、本当に信頼できるレベルか?
- M&Aや組織再編など、会社の未来を左右する選択肢に精通しているか?
ホームページの情報だけでなく、面談で具体的な実績や過去の事例を直接尋ね、その専門性の深さを見極めましょう。
2. あなたの「業界」への理解度
業界には、それぞれ特有の商慣行や会計処理があります。それを理解していない税理士では、的確なアドバイスは期待できません。
- 自社と同じ業界の顧問先はいるか?
- 自社の業界の将来性や課題について、どんな見解を持っているか?
面談の場で、あえて業界に関する専門的な質問を投げかけてみるのも、相手の理解度を測る有効な方法です。
3. 「資金調達」を任せられる支援力
会社の成長戦略を実現するためには、銀行からの融資など、資金調達が生命線となります。
- 金融機関との交渉力や、独自のネットワークを持っているか?
- 銀行が「この会社になら融資したい」と思うような、説得力のある事業計画書を一緒に作れるか?
- 国や自治体の補助金・助成金を積極的に活用するノウハウを持っているか?
これらの支援力こそ、会社の成長をダイレクトに左右する、極めて重要なポイントです。
4. 「守り」だけでなく「攻め」の経営相談ができるか
これからの経営者に必要なのは、現状維持の「守りの経営」ではありません。未来を自ら創り出す「攻めの経営」です。
- 会社の数字を分析し、具体的な改善提案をしてくれるか?
- あなたのビジョンに心から共感し、その実現に向けたロードマップを一緒に考えてくれるか?
- IT導入やDX化といった、新しい経営課題にも対応できる知識と情熱があるか?
単なる税務の専門家ではなく、会社の未来を共に考える「経営パートナー」としての資質があるか、しっかりと見極めましょう。
5. 人としての「相性」
そして最後に、どんなに優れた専門家でも、人間的な相性が合わなければ、本音の付き合いはできません。
- 専門用語を、あなたに分かる言葉で丁寧に説明してくれるか?
- レスポンスは迅速か?気軽に「こんなこと聞いてもいいのかな」と思える雰囲気か?
- 後継者であるあなたの考えや想いを、真摯に、否定せずに受け止めてくれるか?
何度も面談を重ね、会話を通じて、「この人になら、会社の未来を、自分の人生を託せる」と心から思えるかどうかも大切です。
まとめ:事業承継は会社の「第二創業」。未来を共に創る税理士変更が大切!

ここまで、事業承継を機に税理士の変更を考える後継者のために、そのタイミングがなぜ最適なのか、そして未来を託せるパートナーをどう見極めるべきかについて解説してきました。
事業承継は、単に会社を引き継ぐだけの手続きではありません。それは、後継者であるあなたの手で、会社の新しい歴史を創り上げていく「第二の創業」なのです。
- 事業承継の課題: 経営、人事、資金など、後継者が取り組むべき課題は山積み。
- 変更の本当の理由: 根っこにあるのは、未来志向の「資金管理」ができていないことへの不満。
- ベストタイミングな訳: 新ビジョンの共有、しがらみのリセット、新しい経営ノウハウの導入が可能になるから。
- 引き継ぎの最重要点: 書類に残らない「暗黙知」を、新旧の税理士間でいかに共有するかが鍵。
- パートナー選びの5つの着眼点: ①事業承継の実績、②業界理解度、③資金調達力、④攻めの経営相談、⑤そして何より、人としての相性。
先代にとって最高の税理士が、必ずしもあなたの代の最高のパートナーであるとは限りません。過去の数字を処理するだけの「守りの経理」から脱却し、共に汗をかき、会社の未来を語り合える「攻めの経営パートナー」こそが、あなたの「第二の創業」期に、本当にふさわしい存在です。
私たちイデア総研税理士法人は、大分県トップクラスの専門家集団として、これまで数百社以上の税務顧問、1,000件以上の事業承継に関するご相談を支援してまいりました。
事業計画の策定、資金調達、複雑な税務手続き、そして新しい組織づくりまで、事業承継には、この記事で触れた以外にも、数多くの課題が待ち受けています。 それらすべてを、後継者であるあなたが一人で抱え込む必要はありません。
私たちは、その一つひとつの課題を、豊富な実績とノウハウで、あなたと伴走しながら解決に導きます。 「何から手をつければいいかすら、わからない」 そんな漠然とした不安の段階からで、まったく問題ありません。事業承継のご相談があればぜひお気軽にお問い合わせください!